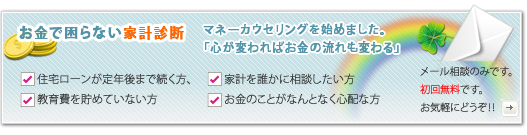2015年03月08日
結婚・子育て資金の一括贈与
今年の4月から平成31年3月まで・・・・
の4年間に限り・・・・
親、祖父母からの結婚・子育て資金贈与については
一定金額まで非課税とする措置が創設されます。
これは・・・
若年層における将来の経済的不安(結婚、出産)が
少子化につながっていることを考慮したものです。
ひとり当たり1000万円まで無税になります。
結婚に際しての費用は300万円までが無税となります。
ただ、贈与に際しての注意点があります。
子ども名義の信託口座を金融機関で作成して
親、祖父母は口座に贈与する分を入金し、
子どもがそのお金を使うには、
結婚、妊娠、出産、育児の領収書を金融機関に提出しなければなりません。
さらに、税務署には金融機関名が入った申告書を提出しなければなりません。
また、贈与した親、祖父母が亡くなった時点で口座に残金があれば
相続税の対象になります。
税金は・・・・
自分には関係ないから・・・・
と思っていると・・・・
知っていると知らないとではずいぶん違ってくることもあります。
そう、お金のことは・・・・
ご相談でお会いすると・・・・
知らないと言うだけで・・・・
ずいぶん損していることもあるのが実情です。
の4年間に限り・・・・
親、祖父母からの結婚・子育て資金贈与については
一定金額まで非課税とする措置が創設されます。
これは・・・
若年層における将来の経済的不安(結婚、出産)が
少子化につながっていることを考慮したものです。
ひとり当たり1000万円まで無税になります。
結婚に際しての費用は300万円までが無税となります。
ただ、贈与に際しての注意点があります。
子ども名義の信託口座を金融機関で作成して
親、祖父母は口座に贈与する分を入金し、
子どもがそのお金を使うには、
結婚、妊娠、出産、育児の領収書を金融機関に提出しなければなりません。
さらに、税務署には金融機関名が入った申告書を提出しなければなりません。
また、贈与した親、祖父母が亡くなった時点で口座に残金があれば
相続税の対象になります。
税金は・・・・
自分には関係ないから・・・・
と思っていると・・・・
知っていると知らないとではずいぶん違ってくることもあります。
そう、お金のことは・・・・
ご相談でお会いすると・・・・
知らないと言うだけで・・・・
ずいぶん損していることもあるのが実情です。
2015年01月09日
世界一高い相続税
今年の1月から相続税が変更になりました。
大きな変更点は5つ・・・・
1、基礎控除額の減額
基礎控除が6割に縮小されました.
以前なら・・・・
相続人が妻と子供1人の場合、
5000万円+法定相続人の数×1000万円
例えば・・・・
遺産総額が7000万円まで非課税でしたが・・・
1月からは・・・
3000万円+法定相続人の数×600万円に減額になりました。
2、最高税率の引き上げと税率の変更
相続税の税率が引き上げられています。
以前は最高50%でしたが、最高55%の税金がかかることになります。
3、未成年者や障害者の控除額引き上げ
未成年者控除については・・・
以前は 20歳になるまでの1年につき
6万円が改正で10万円になります。
また、障害者控除は・・・・
以前は85歳になるまでの1年につき6万円でしたが・・・・
改正後は10万円になります。
但し、特別障害者の場合には12万円が20万円になります。
4、小規模宅地等の特例の拡充
以前は240平方メートルまでとされる自宅の敷地面積が・・・・
330平方メートルまで拡大されました。
改正案に上がっていた、生命保険金の非課税枠の縮小は・・・・
見送りとなり改正になりませんでした。
大きな変更点は5つ・・・・
1、基礎控除額の減額
基礎控除が6割に縮小されました.
以前なら・・・・
相続人が妻と子供1人の場合、
5000万円+法定相続人の数×1000万円
例えば・・・・
遺産総額が7000万円まで非課税でしたが・・・
1月からは・・・
3000万円+法定相続人の数×600万円に減額になりました。
2、最高税率の引き上げと税率の変更
相続税の税率が引き上げられています。
以前は最高50%でしたが、最高55%の税金がかかることになります。
3、未成年者や障害者の控除額引き上げ
未成年者控除については・・・
以前は 20歳になるまでの1年につき
6万円が改正で10万円になります。
また、障害者控除は・・・・
以前は85歳になるまでの1年につき6万円でしたが・・・・
改正後は10万円になります。
但し、特別障害者の場合には12万円が20万円になります。
4、小規模宅地等の特例の拡充
以前は240平方メートルまでとされる自宅の敷地面積が・・・・
330平方メートルまで拡大されました。
改正案に上がっていた、生命保険金の非課税枠の縮小は・・・・
見送りとなり改正になりませんでした。
2014年12月15日
「夫婦控除」の導入・・・
専業主婦やパートの妻の控除である
「配偶者控除」ですが・・・
これを見直す動きがあります。
今までは妻の収入103万円以下に
「配偶者控除」されていました。
これを・・・・
妻の収入にかかわらず
一定額を夫の所得から差し引く
「夫婦控除」を2016年度以降に実施予定です。
配偶者控除は・・・・
1961年に所得税。
1966年に住民税の減額導入されました。
終身雇用の夫と無職又はパートの妻で構成された
旧来型の雇用情勢から由来されています。
ただ、現在の日本では旧来型の家族の在り方も
変わってきています。
つまり、働き方、家族構成など・・・・
現状では合わなくなってきています。
この配偶者控除を・・・
妻の収入にかかわらず
一定額を夫の所得から差し引く
「夫婦控除」を2016年度以降に実施予定です。
これにより・・・・
現在控除対象の1400万人いるうちのパート勤務の収入にも所得税が
かかる方向になります。
政府の考え方としては・・・・
配偶者控除の枠で働くために
雇用を調整する動きを止め雇用の拡大をはかりたい。
また共働き夫婦の不公平感の是正。
更に、社会保険料の負担を減少させる
など・・・・
様々な理由があります。
つまり・・・
今後は103万円の枠で働いても・・・・
手取りの収入は減る傾向にあります。
今、今後将来の生活が厳しいかも・・・・
と思われるなら・・・・
これを、見直しのチャンスととらえるのか・・・・
そのまま流されるのか・・・・
選択の違いが・・・・
10年後の生活に違いが出てきます。
また、今後はお金を増やすことも大切ですが、
減らさないことも大切になってきます。
「配偶者控除」ですが・・・
これを見直す動きがあります。
今までは妻の収入103万円以下に
「配偶者控除」されていました。
これを・・・・
妻の収入にかかわらず
一定額を夫の所得から差し引く
「夫婦控除」を2016年度以降に実施予定です。
配偶者控除は・・・・
1961年に所得税。
1966年に住民税の減額導入されました。
終身雇用の夫と無職又はパートの妻で構成された
旧来型の雇用情勢から由来されています。
ただ、現在の日本では旧来型の家族の在り方も
変わってきています。
つまり、働き方、家族構成など・・・・
現状では合わなくなってきています。
この配偶者控除を・・・
妻の収入にかかわらず
一定額を夫の所得から差し引く
「夫婦控除」を2016年度以降に実施予定です。
これにより・・・・
現在控除対象の1400万人いるうちのパート勤務の収入にも所得税が
かかる方向になります。
政府の考え方としては・・・・
配偶者控除の枠で働くために
雇用を調整する動きを止め雇用の拡大をはかりたい。
また共働き夫婦の不公平感の是正。
更に、社会保険料の負担を減少させる
など・・・・
様々な理由があります。
つまり・・・
今後は103万円の枠で働いても・・・・
手取りの収入は減る傾向にあります。
今、今後将来の生活が厳しいかも・・・・
と思われるなら・・・・
これを、見直しのチャンスととらえるのか・・・・
そのまま流されるのか・・・・
選択の違いが・・・・
10年後の生活に違いが出てきます。
また、今後はお金を増やすことも大切ですが、
減らさないことも大切になってきます。
2014年10月08日
配偶者控除見直し
よくご相談者の方で・・・・
103万円までは税金はかからないから・・・
その103万円を超えて働くことは損でしょうか?
という質問をよく聞きます。
ではこの103万円ですが・・・
どういう仕組みになっているのかを理解している人は
少ないようです。
まずは基本を抑える必要があります。
収入と所得の違いです。
収入は・・・・
1年間に得た収入額の総額になります。
所得とは・・・・
収入から一定額の経費を引いた金額になります。
例えば・・・・
働くためには、ある程度の経費が必要になります。
働くために洋服や靴やバックなどが必要になることも
あります。(実際必要でなくてもOK)
その経費として、給与を貰っている人は・・・
65万円を引くことができます。
この65万円控除額を所得控除といいます。
つまり・・・
103万円の収入から65万円の経費を引くと・・・
38万円の所得となります。
38万円の所得なのでこの金額に所得税がかかることになります。
しかし、実際には更に人が生きて行く最低限の控除があります。
その金額が・・・
基礎控除38万円になります。
つまり・・・
所得38万円までは税金がかからないということになります。
上記のケースはあくまで所得税のお話になりますので・・・
住民税は、103万円でも住民税の対象になることもあります。
基本をおさえたところで・・・
今回問題になっている配偶者控除のお話・・・
まず、配偶者控除とは・・・
夫に扶養されている妻の給与収入が年間103万円以下の場合に
夫の所得から38万円を差し引くことで、
夫の所得税負担を軽減する仕組みのことです。
現在、約1400万人がその対象となっています。
専業主婦のいる高所得者世帯ほど税制面の恩恵を
受けているとの問題が指摘されているという現実があります。
最近では、女性の雇用を促進しようという動きや・・・・
所得控除の不公平感などで・・・
常に・・・議論の対象になってきました。
今回はこの配偶者控除の見直しが議論されました。
長期的な税制のあり方を検討する政府税制調査会です。
将来に向けて・・・専業主婦世帯でも共働き世帯でも不公平感を軽減できるように・・・
そのいくつかのアイディアとは・・・・
1、配偶者控除を見直し、夫婦それぞれが基礎控除を持ち、妻が使いきれない場合には夫が使える仕組みに。
パート世帯には負担増
2、配偶者控除を見直し、所得にかかわらず税負担を一定に抑える方式。高所得者は負担増に
3、配偶者控除をなくす一方で、所得税から一定額を差し引く「税額控除」を導入。
専業主婦の世帯と共働きの世帯で税負担の軽減額が同じに
4、配偶者控除をなくす一方で、子育てを支援する控除制度を創設
今回の議論は以前からたびたび問題になっていました。
この配偶者控除を変更することで、次の税金への議論になるかもしれません。
国の足りない生活費と借金返済の金額を・・・
どこから持ってこようか・・・
という議論にならないように・・・
税金問題も人ごとではない大切な話になります。
103万円までは税金はかからないから・・・
その103万円を超えて働くことは損でしょうか?
という質問をよく聞きます。
ではこの103万円ですが・・・
どういう仕組みになっているのかを理解している人は
少ないようです。
まずは基本を抑える必要があります。
収入と所得の違いです。
収入は・・・・
1年間に得た収入額の総額になります。
所得とは・・・・
収入から一定額の経費を引いた金額になります。
例えば・・・・
働くためには、ある程度の経費が必要になります。
働くために洋服や靴やバックなどが必要になることも
あります。(実際必要でなくてもOK)
その経費として、給与を貰っている人は・・・
65万円を引くことができます。
この65万円控除額を所得控除といいます。
つまり・・・
103万円の収入から65万円の経費を引くと・・・
38万円の所得となります。
38万円の所得なのでこの金額に所得税がかかることになります。
しかし、実際には更に人が生きて行く最低限の控除があります。
その金額が・・・
基礎控除38万円になります。
つまり・・・
所得38万円までは税金がかからないということになります。
上記のケースはあくまで所得税のお話になりますので・・・
住民税は、103万円でも住民税の対象になることもあります。
基本をおさえたところで・・・
今回問題になっている配偶者控除のお話・・・
まず、配偶者控除とは・・・
夫に扶養されている妻の給与収入が年間103万円以下の場合に
夫の所得から38万円を差し引くことで、
夫の所得税負担を軽減する仕組みのことです。
現在、約1400万人がその対象となっています。
専業主婦のいる高所得者世帯ほど税制面の恩恵を
受けているとの問題が指摘されているという現実があります。
最近では、女性の雇用を促進しようという動きや・・・・
所得控除の不公平感などで・・・
常に・・・議論の対象になってきました。
今回はこの配偶者控除の見直しが議論されました。
長期的な税制のあり方を検討する政府税制調査会です。
将来に向けて・・・専業主婦世帯でも共働き世帯でも不公平感を軽減できるように・・・
そのいくつかのアイディアとは・・・・
1、配偶者控除を見直し、夫婦それぞれが基礎控除を持ち、妻が使いきれない場合には夫が使える仕組みに。
パート世帯には負担増
2、配偶者控除を見直し、所得にかかわらず税負担を一定に抑える方式。高所得者は負担増に
3、配偶者控除をなくす一方で、所得税から一定額を差し引く「税額控除」を導入。
専業主婦の世帯と共働きの世帯で税負担の軽減額が同じに
4、配偶者控除をなくす一方で、子育てを支援する控除制度を創設
今回の議論は以前からたびたび問題になっていました。
この配偶者控除を変更することで、次の税金への議論になるかもしれません。
国の足りない生活費と借金返済の金額を・・・
どこから持ってこようか・・・
という議論にならないように・・・
税金問題も人ごとではない大切な話になります。
2014年09月11日
死んでも税金がかかる?
国の借金が過去最大になり・・・・
個人からの税金が加速しています。
今年4月からは消費税が8%になりました。
更に来年10月には10%になる予定です。
また、来年には所得税や相続税の控除が
下がり負担が増えることになります。
今までは・・・・
相続税なんて関係ない・・・
と思っていた人にも・・・・
関係してくる可能性が高くなります。
今まで相続税を支払ったケースは全体の相続の4%程度でした。
現行なら・・・・
5,000万円+1,000万円×法定相続人数の基礎控除があります。
それが・・・・
平成27年1月1日以後の相続から・・・・
3,000万円+600万円×法定相続人数となります。
また、政府では高齢者の医療保険などが毎年増えていくので・・・
それらを補うために・・・
死亡消費税を検討しています。
これは・・・・
死亡時に残した財産から一定の税率で税金を徴収するというものです。
死んでも税金を払わなくてはいけなくなる日が・・・
もしかしたら・・・・
近いかもしれません。
個人からの税金が加速しています。
今年4月からは消費税が8%になりました。
更に来年10月には10%になる予定です。
また、来年には所得税や相続税の控除が
下がり負担が増えることになります。
今までは・・・・
相続税なんて関係ない・・・
と思っていた人にも・・・・
関係してくる可能性が高くなります。
今まで相続税を支払ったケースは全体の相続の4%程度でした。
現行なら・・・・
5,000万円+1,000万円×法定相続人数の基礎控除があります。
それが・・・・
平成27年1月1日以後の相続から・・・・
3,000万円+600万円×法定相続人数となります。
また、政府では高齢者の医療保険などが毎年増えていくので・・・
それらを補うために・・・
死亡消費税を検討しています。
これは・・・・
死亡時に残した財産から一定の税率で税金を徴収するというものです。
死んでも税金を払わなくてはいけなくなる日が・・・
もしかしたら・・・・
近いかもしれません。
2014年02月06日
インフレ大増税でダブルパンチ
皆さんがご存じのように・・・・
消費税率は14年4月に8%に引き上がる予定になっています。
ある試算では、
消費増税に伴う家計負担は年収300万円未満世帯の年間で平均約6万円、
年収1000万円以上世帯で約14万2円増加することになります。
これはあくまで、一般的な家庭を対象としていますので、多少の前後はあります。
さらに・・・
増税は・・・・
2037年12月末まで、東日本大震災の復興に充てるための復興増税として・・・
所得税額に2.1%が加わることになります。
これは・・・
特別法人税は廃止されて個人の所得から負担となります。
2014年は個人からの増税がかなり大幅になされる代わりに企業の税金が優遇される
傾向が強くなります。
更に・・・
今株式に個人の資金が流入していますが・・・
NISA(ニーサ)以外の株式の配当金や運用益などにかかる所得税や住民税は、
14年1月からは10%から20%(復興税分を除く)に戻ります。
つまり・・・
多少のお金があればどんどんと増税をしますよという政策に変換されてきています。
特に・・・・
年収1200万円超のサラリーマンは所得税と住民税が大幅に増えることになります。
もちろん・・・
年収1200万円のサラリーマンは自分には関係ないと言われるかもしれません。
ただ・・・
ここにきて・・・・
物価も上昇傾向にあります。
総務省が2013年12月の消費者物価指数を発表した内容によると・・・
代表的な指標である「生鮮食品を除く総合(コア指数)」は
前年同月比でプラス1.3%と先月に引き続いて上昇となっています。
つまり・・・
ほとんどの人にも影響のある増税とインフレがダブルで・・・
家計に影響を及ぼすことになりそうです。
上記に備えて・・・・
見直しは将来家計を守ることにも・・・・
なります。
消費税率は14年4月に8%に引き上がる予定になっています。
ある試算では、
消費増税に伴う家計負担は年収300万円未満世帯の年間で平均約6万円、
年収1000万円以上世帯で約14万2円増加することになります。
これはあくまで、一般的な家庭を対象としていますので、多少の前後はあります。
さらに・・・
増税は・・・・
2037年12月末まで、東日本大震災の復興に充てるための復興増税として・・・
所得税額に2.1%が加わることになります。
これは・・・
特別法人税は廃止されて個人の所得から負担となります。
2014年は個人からの増税がかなり大幅になされる代わりに企業の税金が優遇される
傾向が強くなります。
更に・・・
今株式に個人の資金が流入していますが・・・
NISA(ニーサ)以外の株式の配当金や運用益などにかかる所得税や住民税は、
14年1月からは10%から20%(復興税分を除く)に戻ります。
つまり・・・
多少のお金があればどんどんと増税をしますよという政策に変換されてきています。
特に・・・・
年収1200万円超のサラリーマンは所得税と住民税が大幅に増えることになります。
もちろん・・・
年収1200万円のサラリーマンは自分には関係ないと言われるかもしれません。
ただ・・・
ここにきて・・・・
物価も上昇傾向にあります。
総務省が2013年12月の消費者物価指数を発表した内容によると・・・
代表的な指標である「生鮮食品を除く総合(コア指数)」は
前年同月比でプラス1.3%と先月に引き続いて上昇となっています。
つまり・・・
ほとんどの人にも影響のある増税とインフレがダブルで・・・
家計に影響を及ぼすことになりそうです。
上記に備えて・・・・
見直しは将来家計を守ることにも・・・・
なります。
2013年11月06日
会社員の経費拡大
今日の日経にも載っていましたが・・・
特定支出控除と言う言葉を聞いたことがありますか。
これは・・・
1987年に会社員の一定の経費を必要経費として税金控除として
申告できるようになったものです。
ただ、実際にはこれを活用できるまでには至っていない経緯があります。
なぜなら・・・
給与の所得控除額を上回る必要があったからです。
これが・・・
平成25年分の所得から・・・
給与所得控除額の2分の1に緩和されました。
例として・・・
年収400万円の平均的な給与所得控除額の2分の1の金額は67万円程度
なのでこの金額を超える特定支出が所得控除の対象になります。
対象の項目は・・・
① 通勤費 通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出
② 通勤費 通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出
③研修費 職務の遂行に直接必要な知識等を習得するための研修に要する支出
④資格取得費 資格を取得するための支出でその者の職務に直接必要であるもの
⑤帰宅旅費
転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする
こととなった場合等において、勤務する場所と配偶者が居
住する場所等との間の旅行に要する支出
⑥勤務必要経費
図書費・衣服費・
交際費等
※上限65 万円
職務に関連する図書を購入するための支出・勤務場所にお
いて着用することが必要とされる衣服を購入するための
支出・給与等の支払者の得意先、仕入先などの職務上関係
のある方に対する接待等のための支出
例えば・・・
スーツを購入した場合にもこの対象になります。
(但し、会社で着ることが前提です)
また、
会社で必要とされる図書費も対象になります。
但し、注意が必要です。
会社の承認が必要なことそのための領収書が必要です。
また、確定申告が必要になります。
証明書の用紙は国税庁のホームページで公開しています。
詳しくは・・・
国税庁のホームページで確認してみてください。
2013年08月28日
軽自動車増税になる?
現在、軽自動車の人気が上がっています。
2013年7月の軽自動車国内販売台数は、
前年同月比1.7%増の18万7797台.
3カ月ぶりに前年実績を上回り、7月としては過去最高となっています。
この軽自動車の人気を支える原因として・・・
性能がUPや税金が安いなどがよく取り上げられています。
ここにきて・・・
TPP(環太平洋パートナーシップ)、日欧経済連携協定(EPA)の絡みや
赤字国債に伴う財源確保などから
軽自動車優遇撤廃が議論されそうです。
現状の税金は
軽自動車・・・・・7200円で格段に安くなっています。
この税金を数千円上げると千億単位の税金の確保ができると言われています。
消費税UPに合わせてもしかしたら、
UPする可能性がありそうです。
2013年02月21日
会社員の確定申告
会社員で確定申告だと・・・
代表的なものが・・・
住宅を購入した場合の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)や
医療費控除を思い浮かべる方が多いと思います。
よく忘れがちなのが、1年の途中で退職しその後再就職しなかったケースです。
この場合には会社で毎年行う年末年末調整をしていないので、
確定申告をすることで、所得税の払いすぎの部分が還付されます。
先日お会いした方は、途中で退職して、確定申告をしなかったとのことです。
ちなみに、還付の場合には3月15日を過ぎても受付をしてもらえます。
代表的なものが・・・
住宅を購入した場合の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)や
医療費控除を思い浮かべる方が多いと思います。
よく忘れがちなのが、1年の途中で退職しその後再就職しなかったケースです。
この場合には会社で毎年行う年末年末調整をしていないので、
確定申告をすることで、所得税の払いすぎの部分が還付されます。
先日お会いした方は、途中で退職して、確定申告をしなかったとのことです。
ちなみに、還付の場合には3月15日を過ぎても受付をしてもらえます。
2013年02月07日
年金の確定申告
以前でしたら、年金受給者は毎年確定申告をしていました。
これが・・・
2011年分より、公的年金の受給額が400万円以下で、
その他所得が20万円以下の人は、確定申告をしないで済みます。
毎年の面倒な作業がなくなってほっとしている方も多いかと思います。
ただ、所得税の確定申告をすることで住民税も変わってくることがあります。
特に生命保険料控除・地震控除や医療費控除がある場合には申告によっては、
翌年の住民税が高くなったり、
70歳以上なら住民税によって、医療費負担額が1割のところが3割負担になる
こともあり得ます。
まわりに年金受給の知人や親族がいれば、声をかけてあげるといいかと思います。
面倒だから・・・しないは損する可能性もあります。
これが・・・
2011年分より、公的年金の受給額が400万円以下で、
その他所得が20万円以下の人は、確定申告をしないで済みます。
毎年の面倒な作業がなくなってほっとしている方も多いかと思います。
ただ、所得税の確定申告をすることで住民税も変わってくることがあります。
特に生命保険料控除・地震控除や医療費控除がある場合には申告によっては、
翌年の住民税が高くなったり、
70歳以上なら住民税によって、医療費負担額が1割のところが3割負担になる
こともあり得ます。
まわりに年金受給の知人や親族がいれば、声をかけてあげるといいかと思います。
面倒だから・・・しないは損する可能性もあります。